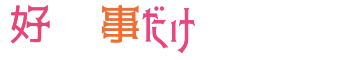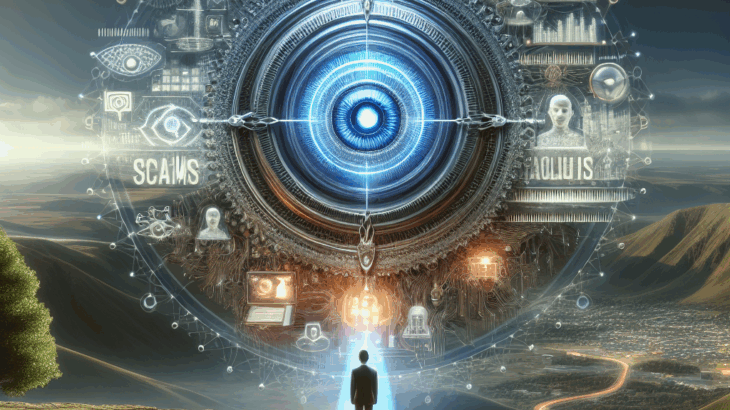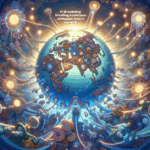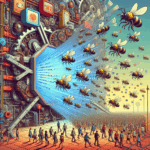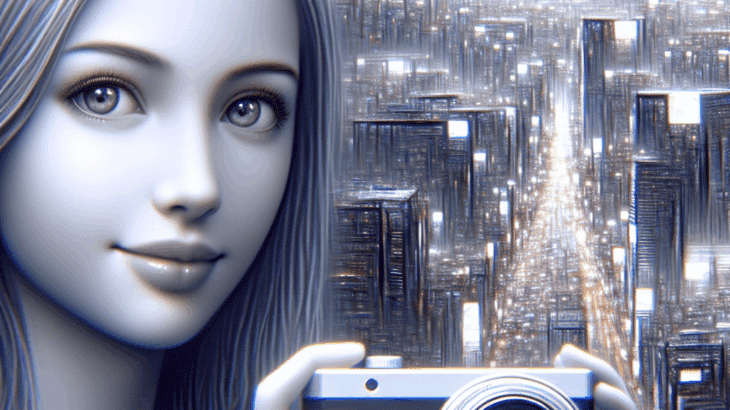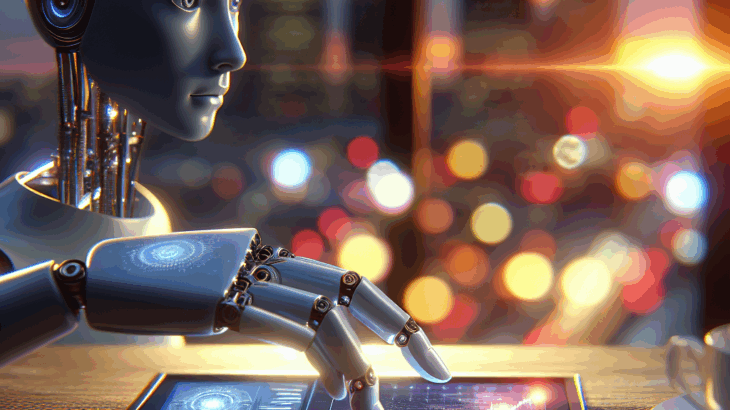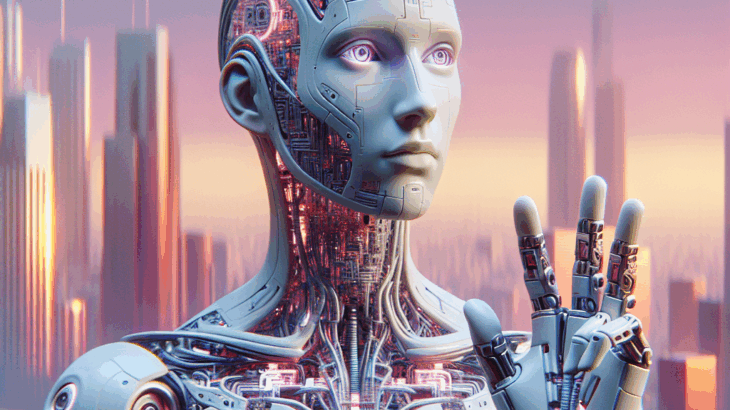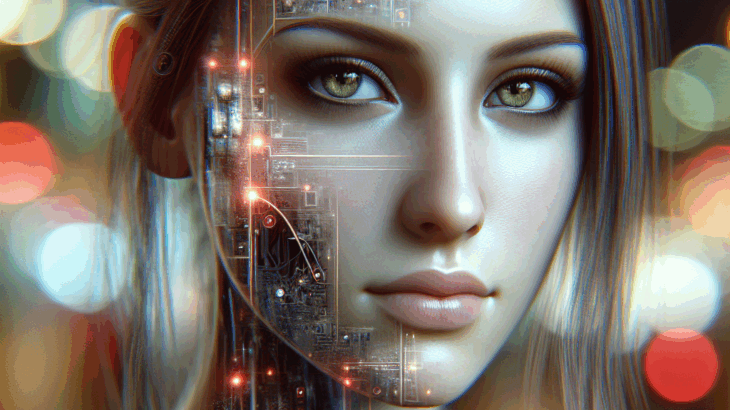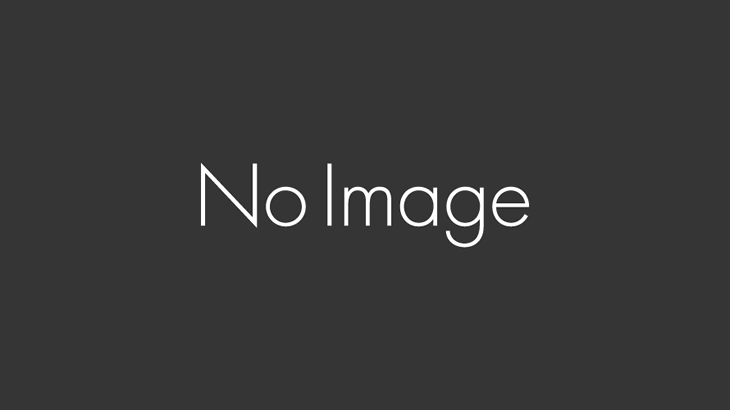生成AI時代におけるゼロトラストセキュリティの再考
2025年11月現在、生成AIの急速な進化は、サイバーセキュリティの様相を大きく変えつつあります。従来の境界防御型セキュリティモデルは、生成AIを活用した高度な攻撃に対して脆弱性を露呈しており、ゼロトラストアーキテクチャの重要性が改めて認識されています。本稿では、生成AI時代のリスクと機会を考慮し、ゼロトラストセキュリティ戦略を再考します。
生成AIがもたらすセキュリティリスク
生成AIは、高度なフィッシング詐欺、ディープフェイクを用いたなりすまし、マルウェアの自動生成など、サイバー攻撃の高度化と自動化を促進します。特に、ソーシャルエンジニアリング攻撃においては、生成AIが個人の行動パターンや嗜好を分析し、より巧妙な騙し文句を作成することで、従来のセキュリティ対策を容易に突破する可能性があります。
- 高度なフィッシング攻撃: 個人情報を詐取するメールやメッセージの精度が向上。
- ディープフェイクによるなりすまし: 音声や映像を合成し、信頼できる人物を装う攻撃。
- マルウェアの自動生成: セキュリティ対策を回避するマルウェアを自動で生成。
ゼロトラストアーキテクチャの原則
ゼロトラストは、「決して信用せず、常に検証する」という原則に基づき、ネットワークの内外を問わず、全てのアクセス要求を検証するセキュリティモデルです。主な要素は以下の通りです。
- マイクロセグメンテーション: ネットワークを細分化し、アクセス範囲を最小限に限定。
- 多要素認証 (MFA): パスワードだけでなく、複数の認証要素を組み合わせることで、不正アクセスを防止。
- 最小特権の原則: ユーザーに必要最小限の権限のみを付与し、特権アカウントの悪用リスクを低減。
- 継続的な監視と分析: ネットワークトラフィックやユーザー行動を常に監視し、異常を検知。
成功事例と失敗事例
ある金融機関では、ゼロトラストアーキテクチャを導入し、マイクロセグメンテーションによって内部ネットワークを細分化しました。これにより、万が一、一部のシステムが侵害された場合でも、被害範囲を最小限に抑えることが可能になりました。しかし、導入初期段階では、厳格なアクセス制御が業務効率を低下させるという課題も発生しました。この課題に対しては、ユーザーへの丁寧な説明とトレーニングを実施することで、理解と協力を得ることができました。
一方、ある製造業では、ゼロトラスト導入時に、既存のセキュリティ対策との連携を十分に考慮しなかったため、システム間の連携がうまくいかず、かえってセキュリティホールを作り出すという失敗事例も見られました。ゼロトラストの導入は、既存のシステム環境や業務プロセスを十分に理解した上で、段階的に進めることが重要です。
生成AI時代のゼロトラスト戦略
生成AI時代においては、以下の点を考慮したゼロトラスト戦略が求められます。
- AIを活用した脅威インテリジェンス: 生成AIを活用して、新たな脅威を早期に検知し、対応策を自動的に生成。
- AIによるアクセス制御の強化: ユーザーの行動パターンやコンテキストに基づいて、動的にアクセス権限を調整。
- AIによるセキュリティ教育: 生成AIを活用して、従業員向けのセキュリティ教育コンテンツを自動生成し、効果的なトレーニングを実施。
今後の展望
生成AIの進化は、サイバーセキュリティの脅威と機会の両方をもたらします。企業は、生成AIのリスクを理解し、ゼロトラストアーキテクチャを積極的に導入することで、より強固なセキュリティ体制を構築する必要があります。また、AIを活用したセキュリティ対策の開発も不可欠であり、継続的な技術革新が求められます。