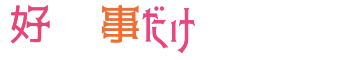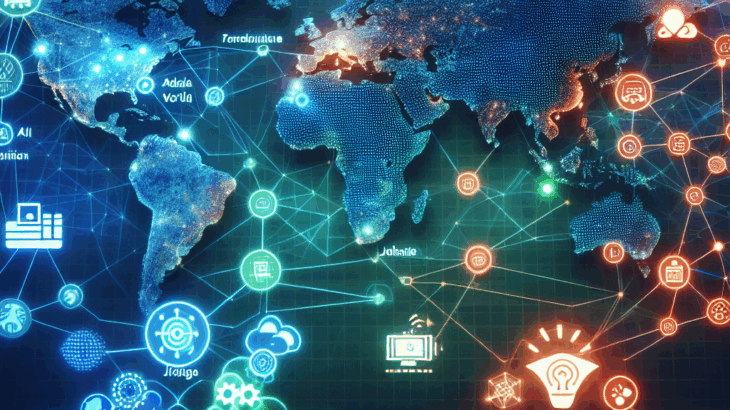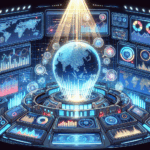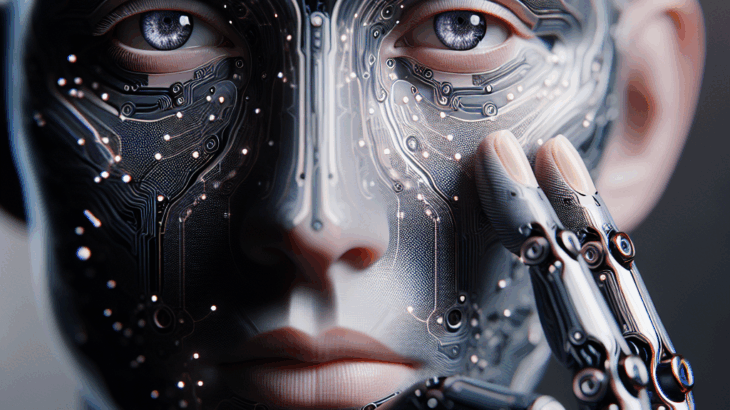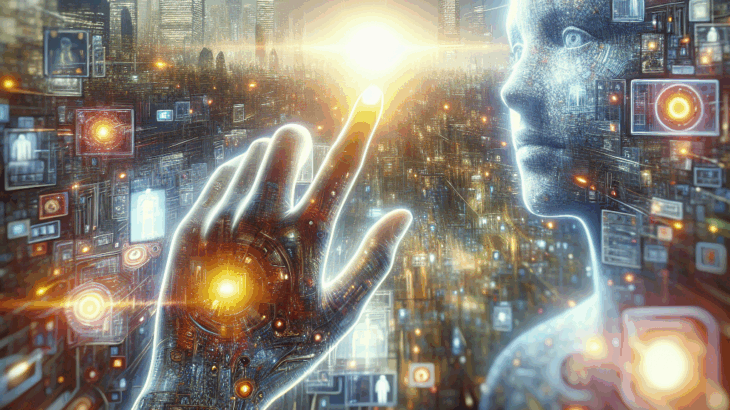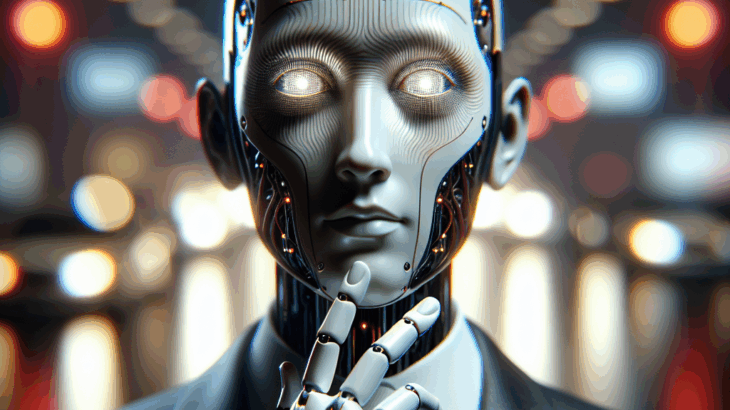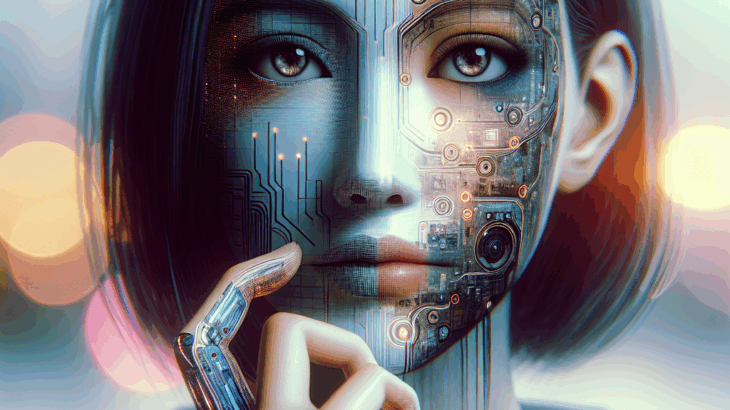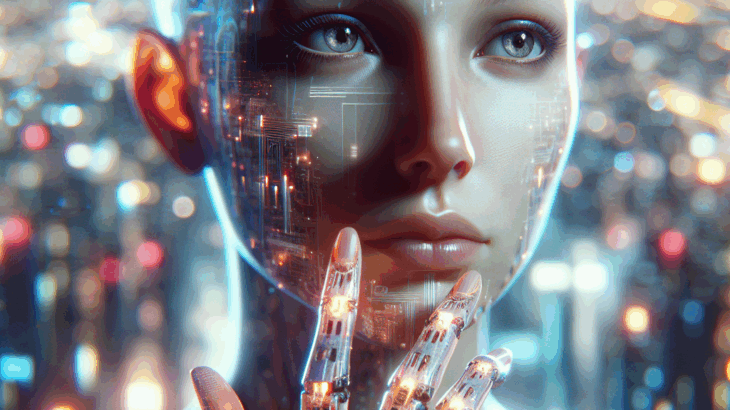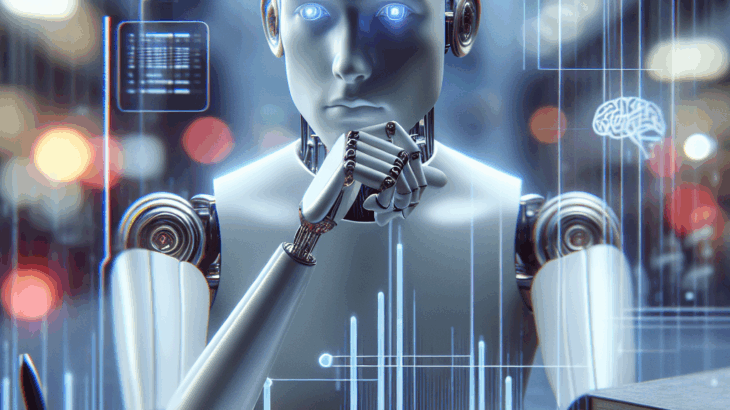エッジAIとゼロトラスト:進化するセキュリティとインテリジェンスの融合
2025年11月現在、エッジAIとオンデバイスAI、そしてサイバーセキュリティとゼロトラストは、ビジネスとテクノロジーの最前線で重要な役割を果たしています。本稿では、これらの分野における日本と海外の動向を比較し、実務で役立つ示唆を提供します。
エッジAIとオンデバイスAI:分散型インテリジェンスの進展
エッジAIとオンデバイスAIは、クラウドに依存せず、デバイス自体またはネットワークのエッジでデータ処理を行う技術です。これにより、低遅延、高プライバシー、帯域幅の節約といったメリットが得られます。
日本の動向
日本では、製造業、自動車産業、ヘルスケア分野でエッジAIの導入が進んでいます。特に、工場の予知保全、自動運転、遠隔医療などの分野で、リアルタイムなデータ分析と迅速な意思決定が求められるため、エッジAIの需要が高まっています。しかし、海外と比較して、AI人材の不足や、規制の遅れが課題となっています。
海外の動向
海外では、特に米国と中国がエッジAIの分野で先行しています。米国では、Amazon、Google、Microsoftなどの大手テクノロジー企業が、エッジAIプラットフォームの開発と普及に力を入れています。中国では、政府の強力な支援のもと、スマートシティ、自動運転、監視システムなどの分野でエッジAIの応用が進んでいます。
サイバーセキュリティとゼロトラスト:信頼から検証へ
従来のサイバーセキュリティは、ネットワークの内側を信頼し、外側を警戒する境界型セキュリティが主流でした。しかし、クラウドサービスの普及やリモートワークの増加により、境界が曖昧になり、従来のセキュリティモデルでは対応が難しくなっています。そこで、ゼロトラストという新しいセキュリティモデルが注目されています。ゼロトラストは、「何も信頼しない、常に検証する」という原則に基づき、ネットワークの内外を問わず、すべてのアクセスを検証します。
日本の動向
日本では、政府がゼロトラストの導入を推奨しており、金融機関や大手企業を中心に導入が進んでいます。しかし、ゼロトラストの導入には、既存のシステムやプロセスを大幅に見直す必要があり、技術的な課題やコストの問題が障壁となっています。
海外の動向
海外では、特に米国がゼロトラストの分野で先行しています。米国政府は、連邦政府機関に対してゼロトラストアーキテクチャの導入を義務付けており、国防総省(DOD)もゼロトラスト戦略を発表しています。また、民間企業でも、Google、Microsoft、Ciscoなどの大手企業が、ゼロトラストソリューションを提供しています。
実務への示唆
- エッジAI導入の際は、具体的なユースケースを明確にし、ROIを評価する。スモールスタートでPoC(Proof of Concept)を実施し、段階的に導入範囲を拡大することが推奨されます。
- ゼロトラスト導入の際は、現状のセキュリティ体制を評価し、リスクアセスメントを実施する。優先順位をつけ、段階的にゼロトラストアーキテクチャを導入することが効果的です。
- 人材育成の重要性:エッジAIとゼロトラストの導入には、高度な専門知識を持つ人材が必要です。企業は、AIエンジニア、セキュリティエンジニアの育成に力を入れる必要があります。
エッジAIとゼロトラストは、相互に補完し合う関係にあります。エッジAIを活用することで、リアルタイムな脅威検知やインシデント対応が可能になり、ゼロトラストのセキュリティレベルを向上させることができます。企業は、これらの技術を統合的に活用することで、より安全で効率的なビジネス環境を構築することができます。