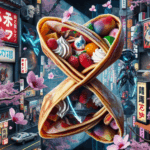都会の夜は、光りと闇が交錯している。職場から帰ると、何もかもが疲れているようだ。歩道橋を渡った先には、酔いどれた男たちが声を張り上げている。彼らは自分たちの喜びや悲しみを歌っているようだ。
私は、そんな風景を眺めながら、足早に歩いていた。遠くには、大きな都市の灯りが見えて、まるで人々が家に帰ろうとしているようだ。私も同じように、今日の一日の疲れを忘れて、自分の時間を過ごそうと思った。
バーに入ったとき、誰もが酔っている。誰かが私を見つけて、助けを求めるように声をかけたが、私は首を振って断った。今日は、自分自身の時間を過ごしたいと思っていた。
グラスに注がれたウイスキーは、温かな光を放っていた。私は一口飲み、その感触が体を伝わっていくのを感じた。もう少し、このままでいたいと思ったが、やがて帰ることも大切だと思った。
家に着いたとき、すぐにベッドに腰を下ろした。闇が眠りに導いてくれるような気がした。そして、やがて、明るい未来が待っていると信じて、眠りに落ちた。